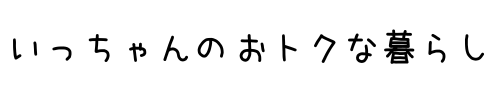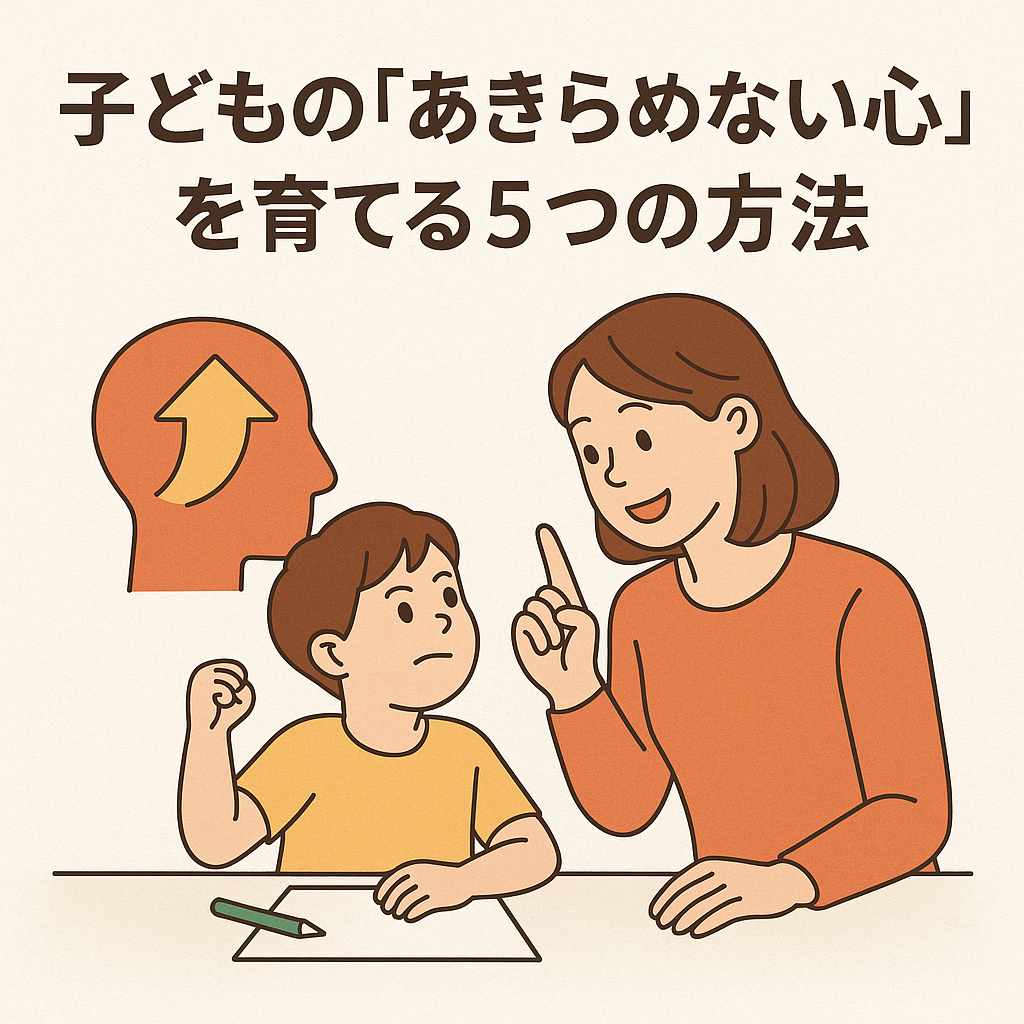― 親の声かけと環境づくりで、少しずつ“粘り強さ”を伸ばす ―
はじめに:最近、子どもがすぐに「もう無理」と言っていませんか?
「ちょっと失敗しただけで“できない!”と投げ出してしまう」
「最後までやりきる前に諦めてしまう」
そんな姿を見ると、親として少し心配になりますよね。
実は、あきらめない心(=レジリエンスやグリット)は生まれつきではなく、家庭での関わり方や環境づくりによって育てられる力です。
この記事では、筆者自身の子育て経験と心理学的な研究をもとに、
子どもの「あきらめない心」を育むための5つの実践方法を紹介します。
1.「できたこと」よりも「挑戦したこと」を褒める
結果を褒めるのも大切ですが、努力や挑戦そのものを認める声かけが「もう一度やってみよう」という意欲を生みます。
✅ 例:「できたね!」ではなく「途中で諦めずに頑張ったね」「最後までやったのがすごいね!」
スタンフォード大学・キャロル・ドゥエック博士の研究によると、「能力は伸ばせる」という“成長マインドセット”を持つ子どもは失敗を恐れず挑戦し続ける傾向があります。
親の声かけが、その考え方を育てる第一歩です。
2.小さな「成功体験」を積み重ねる
子どもがすぐ諦めてしまう原因の一つは、達成体験が少ないこと。
いきなり大きな目標を与えるより、達成しやすい“ミニ目標”を設定してみましょう。
🎯 例:「5分だけ集中してやってみよう」「今日は1ページできたらOK!」
達成できたらしっかり褒めて、「やればできる」という感覚を積み重ねることが大切です。
こうした小さな成功体験が、「もう少し頑張ってみよう」という粘り強さにつながります。
3.失敗を“責めない環境”をつくる
「どうしてできないの?」という言葉は、子どもにとって「失敗=悪いこと」という印象を与えます。
その結果、挑戦自体を避けてしまうことも。
💬 声かけ例:「失敗してもいいよ」「次はどうすればうまくいくかな?」
家庭の中で「失敗しても大丈夫」と思える雰囲気をつくることで、
子どもは安心して新しいことに挑戦できるようになります。
4.親自身が「あきらめない姿」を見せる
子どもは親の行動をよく見ています。
あなたが困難に立ち向かう姿を見せるだけで、子どもは自然とその姿勢を学びます。
🧩 例:料理で失敗しても「次はこうしてみよう」と言う
📖 勉強や資格への挑戦を見せる
親が努力する姿を見せることは、言葉以上に強いメッセージになります。
5.「できなかった」経験を一緒に振り返る
あきらめない心を育てるには、反省よりも“分析”が大切です。
「どこでつまずいたのか」「次にどうすればいいか」を一緒に考える時間をつくりましょう。
🗣 例:「どこがうまくいかなかった?」「次はどうすればできそう?」
こうして考える力を育てることで、自己解決力が少しずつ育ちます。
💡 よくある質問(Q&A)
Q1:何歳から始めればいい?
幼児期(3歳頃)からでOKです。小さな挑戦に「もう一回やってみようね」と声をかけるだけでも効果があります。
Q2:怒りすぎたときは?
「さっきは言いすぎたね、ごめんね」と伝えるだけで信頼関係は回復します。完璧な親である必要はありません。
Q3:あきらめ癖は治る?
時間はかかりますが、成功体験+親のサポートで徐々に変化します。焦らず長い目で見守りましょう。
まとめ: “あきらめない心”は毎日の小さな声かけから
- 「できたね!」より「がんばったね!」
- 「失敗してもいいよ」と伝える
- 「小さな成功」を積み重ねる
この3つを意識するだけで、子どもは少しずつ変わっていきます。
“あきらめない心”は、親子で一緒に育てていくものです。
なら、また、ほんじゃね~